「お湯がすぐ冷めてしまう」
「複数回の入浴に備えたい」
「入居者が快適に使えるお風呂にしたい」
そんな悩みを抱える老人ホームは多いものです。
入浴は高齢者の楽しみであり、心身のリラックスや衛生面の維持に欠かせない時間です。その快適性を支えるのが“追い焚き機能”です。お湯の温度を一定に保ち、いつでも気持ちよく入浴できる環境を実現します。
本記事では、既存浴槽への後付け可否や工事方法、費用相場、導入時の注意点をわかりやすく解説しています。安全性と省エネ性を両立した入浴環境づくりの第一歩を一緒に見ていきましょう。

年間1,000施設以上の納入実績!豊富な導入実績により培われたノウハウで、御社に最適なソリューションを提供いたします。まずはお気軽にご相談(無料)下さい。
電話番号:0120-69-7731
※受付時間|10:00~17:00(平日)

紺田眞二 東京支店長 兼 営業部部長
株式会社ダイレオの企画開発部に新卒で入社し、温浴設備に関わる商品の開発・設計に携わりました。
その後、営業部に異動し、温浴施設やホテル・旅館向けの商品を中心に、設計事務所・建設会社・設備会社など多くの取引先に対して、温浴設備やシステムの提案・導入を行ってまいりました。
保有資格:建築設備士/1級管工事施工管理技士/給水装置工事主任技術者/2級福祉住環境コーディネーターなど
追い焚き機能は後付けできる?判断の3つのチェックポイント
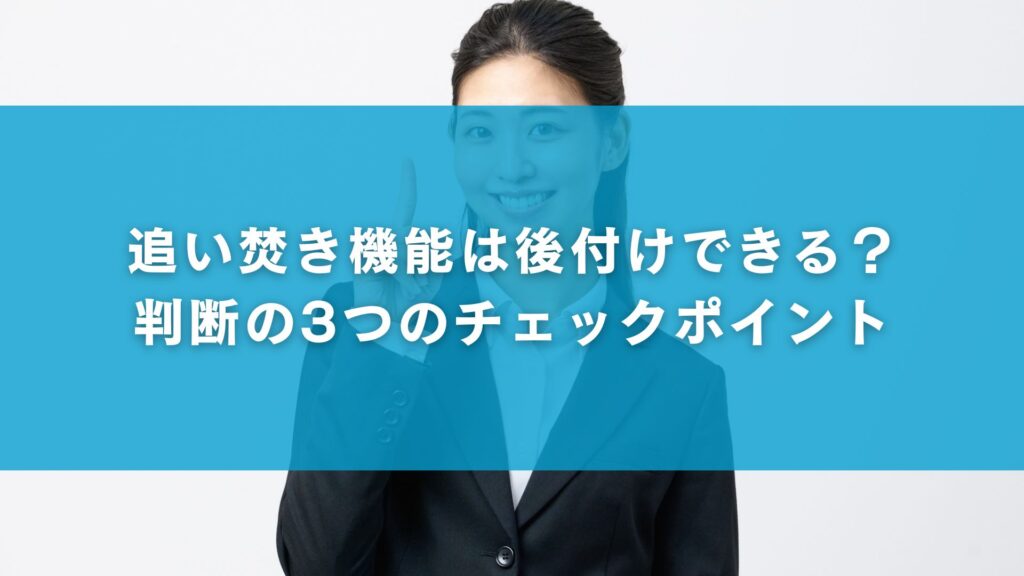
老人ホームに追い焚き機能を導入する場合、まず確認すべきは「後付けできるかどうか」です。浴槽や給湯方式、設置スペースによっては施工が難しいケースもあります。
ここでは、判断に必要な3つのチェックポイントを解説します。
浴槽と給湯方式の組み合わせを確認する
追い焚きの可否は、既存浴槽の構造と給湯システムの方式で決まります。
ユニットバスや在来工法など、浴槽タイプごとに適合性が異なるため、導入前に専門業者による確認が必要です。
ユニットバス:
一体型のため加工が難しいが、循環ユニットを外付けで設置できる場合もある。
在来工法の浴槽:
給湯・排水ルートを確保しやすく、後付けしやすい。
セパレート浴槽:
配管経路が確保できる場合は柔軟に対応可能。
配管と設置スペースの条件を確認する
追い焚きには給湯器→浴槽→循環ユニットを結ぶ配管経路が必要です。
浴槽近くに配管を通せるスペースや、ユニットを設置できる屋外軒下・ベランダなどがあるか確認しましょう。
施工時には次の点を押さえておくことが大切です。
- 既存の配管を流用できるか
- 壁や床の貫通工事が可能か
- 給湯器や制御盤までの距離が近いか
配管経路が確保できれば、循環昇温ユニットのような後付けシステムを導入することで、リフォーム工事を最小限に抑えることができます。
高齢者施設に求められる安全基準を確認する
老人ホームでは、高齢者の安全性と衛生面の配慮が求められます。
特に温度管理・衛生管理・操作性の3点が重要です。
- 温度管理:
入浴時のやけどを防ぐため、設定温度は40℃前後に自動制御されるタイプが安心。
- 衛生管理:
循環経路にたまり湯が残らない構造は、レジオネラ属菌の繁殖防止に有効。
- 操作性:
スタッフが遠隔で設定できるタッチパネル式制御は、介護現場での利便性を高めます。
老人ホームのお風呂へ追い焚き機能を後付けする方法
追い焚き機能を後付けする方法は、大きく分けて3つあります。
施設の規模・浴槽の構造・運用コストに応じて、最適な方式を選ぶことが重要です。
給湯器交換タイプ・循環昇温ユニット・浴槽ヒーターの違い
| 項目 | 給湯器を追い焚き対応型に交換 | 循環昇温ユニット(後付けタイプ) | 浴槽内ヒーター(簡易タイプ) |
| 仕組み | 給湯器を追い焚き対応型に交換し、配管で浴槽と接続 | 浴槽水を循環させて加温。温度ムラが出にくい | 浴槽内ヒーターで直接加温 |
| 導入しやすさ | コンパクトで後付けしやすいが、浴槽工事も必要 | 工事規模がやや大きい(配管接続・浴槽工事・熱源工事が必要)すい | 工事不要。設置が最も簡単 |
| 昇温スピード | 中程度(給湯性能に依存) | 速い。冬季でもスムーズに昇温 | 遅い(湯量が多いと非効率) |
| 衛生性 | 配管内にたまり湯が残ることがある | レジオネラ属菌対策に有効な構造 | 清掃頻度が多く衛生面はやや劣る |
| 費用感 | 中 | 大 | 小 |
| 設置スペース | 屋外に給湯器を設置 | 軒下や浴槽近くに設置可能(別途熱源機等も必要) | 浴槽内のみで完結 |
| おすすめ施設規模 | 老人ホーム・デイサービスなど小・中規模施設向け | 中〜大規模施設向け | 個浴・小規模施設向け |
給湯器を追い焚き対応型に交換する方法
もっとも一般的な方法が、追い焚き対応型の給湯器に交換する方式です。既存配管を利用できる場合、温度制御が安定し、複数浴槽の同時管理にも適しています。
ただし、配管経路が長い場合は熱ロスが発生するため、断熱処理が必要です。また、対応可能な浴槽容量に制限があります。
簡易循環式ユニットを設置する方法
施設リフォームの際に選ばれるのが、循環昇温ユニット(コンパクトタイプ)の後付けです。浴槽水をポンプで循環させながら加温するため、上下の温度差が少なく、昇温スピードが速いのが特長です。
主なメリットは以下の通りです。
・コンパクトで軒下など限られたスペースにも設置可能
・タッチパネル操作で自動保温・湯張りが可能
・湯の出し放しを防ぎ、燃料代を削減
・レジオネラ属菌対策にも有効な構造(塩素滅菌装置を併用可能)
浴槽内ヒーターを活用する方法
小規模施設や個浴では、電気式の浴槽ヒーターを後付けする方法もあります。
施工が不要で導入しやすい一方、加温能力は限定的です。短時間利用や補助的な保温用途として活用すると良いでしょう。
中〜大規模施設では循環昇温ユニットが最もバランスが良く、省エネ性・衛生性・施工性の面で優れています。簡易ヒーターは工事不要ですが、温度維持力や衛生面での課題があるため、短時間利用向けに適しています。


年間1,000施設以上の納入実績!豊富な導入実績により培われたノウハウで、御社に最適なソリューションを提供いたします。まずはお気軽にご相談(無料)下さい。
電話番号:0120-69-7731
※受付時間|10:00~17:00(平日)
追い焚き機能の工期と導入までの流れ
追い焚き機能を後付けする際の工期は、多くのケースで2〜4日程度です。
施設の稼働を止めずに施工できるよう、作業は工程を分けて効率的に進められます。
一般的な導入の流れは次のとおりです。
- 現地調査
浴槽の材質・配管経路・給湯設備の状態を確認。 - 機器選定と見積もり
浴槽容量や利用頻度に応じて、最適な方式を決定。 - 設置工事・配管接続
ユニットや制御盤を設置し、給湯器と接続。 - 試運転と温度設定確認
実際に湯を循環させ、温度制御と安全機能を確認。 - 操作説明・引き渡し
管理者に操作手順とメンテナンス方法を説明。
導入前に知っておくべき注意点と失敗例
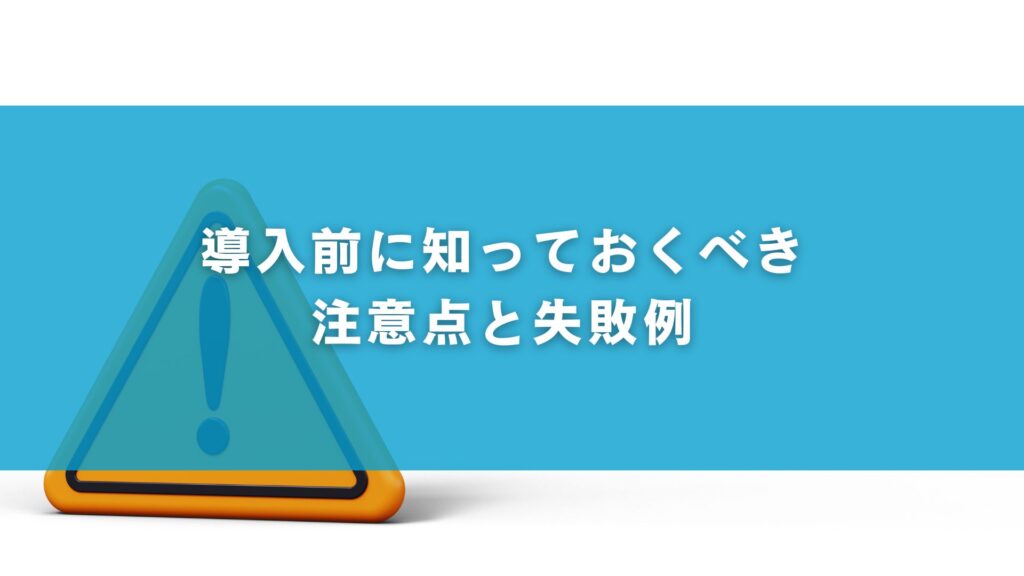
追い焚き機能を後付けする際は、施工環境や運用条件によってトラブルが起こる場合があります。
ここでは代表的な注意点と、導入で失敗しないための対策を紹介します。
既存浴槽の構造によっては後付け不可のケースもある
FRP製や樹脂製の浴槽では、貫通加工が難しいことがあります。
温度管理の不備がレジオネラ属菌リスクにつながる
温度センサーや循環経路の点検を怠ると、湯温が下がり、レジオネラ属菌の繁殖リスクが高まります。
光熱費・メンテナンス負担の増加に注意
追い焚き運転は給湯器への負荷が増えるため、定期点検や定期清掃が重要です。
業者選びで確認すべきポイント
老人ホームでの施工実績があるか、保守体制が明確かを必ず確認しましょう。

まとめ|追い焚き機能の後付けで快適性と運営効率を両立
追い焚き機能の後付けは、老人ホームの入浴環境を大きく改善する有効な手段です。施設規模や浴槽構造に応じた方法を選べば、安全性・衛生性・省エネをすべて両立できます。
後付け可能かどうかの判断に迷った場合は、温浴設備に詳しい専門業者に早めに相談しましょう。

年間1,000施設以上の納入実績!豊富な導入実績により培われたノウハウで、御社に最適なソリューションを提供いたします。まずはお気軽にご相談(無料)下さい。
電話番号:0120-69-7731
※受付時間|10:00~17:00(平日)
=









